「ポテンシャル採用と言ってたのに、“実績不足”で落ちました」
- 「未経験OK」と書いてたのに書類落ち
- 面接で「どんな成果を出しましたか?」と詰められる
- まだ20代前半なのに「実績が足りない」と判断される
──そんな矛盾に、モヤっとしたことはありませんか?
この記事では、企業が“若手にも即戦力を求める”構造的な背景と、
その中でも埋もれないための考え方や行動戦略を、わかりやすく言語化していきます。
なぜ“若手”なのに“実績”が求められるのか?
背景には、OJT依存と“育成コストの放棄”がある
かつての日本企業は「育てる前提」で人材を採用していました。
けれど今、多くの企業が求めているのは――
✅ 「採用したその日から“自走”してくれる人」
✅ 「前職で何か“目に見える成果”を出してきた人」
その理由は、企業側の“育成インフラの弱体化”にあります。
🔹 よくある実態
- OJTが形骸化していて「現場任せ」
- 上司がプレイングマネージャーで“教える余裕”がない
- 新人教育のマニュアルや制度が整っていない
つまり、「育てる余裕がないから“育った人”を欲しがる」という、構造的な矛盾が生まれているのです。
ポテンシャル採用は「嘘」なのか?
嘘ではないが、“リスクの少ない即戦力枠”が優先されやすい
企業側も、「若手を育てたい」と思っていないわけではありません。
ただし現実には…
✅ 「未経験歓迎」としながら、実際に内定が出るのは
- 業界知識が少しでもある人
- 類似業務の経験がある人
- 数字で語れる成果を持っている人
なぜか?
企業にとって、“育てる人材”は投資対象。 だからこそ“リスクの少ないポテンシャル”を優先するんです。
じゃあ、「実績」がない人はどうすればいいのか?
“実績がない”のではなく、“伝わっていない”だけかもしれない
✅ 行動例①:「実績」を“行動×成果”で言語化する
NG:「いろんな仕事を任されていました」
OK:「3ヶ月間でXX件の新規対応を完遂。属人化していた業務をマニュアル化」
→ 小さなエピソードでも、“具体的に・数字で・比較して”話すだけで、実績になる。
✅ 行動例②:「再現性」のある工夫を言語化する
→ 何を考え、どう動き、どんな工夫をしたかを“再現できる形”で語ると、評価が上がる✅ 行動例③:「伸び代」より「伸び方」を見せる
→ 未経験でも、「どうやってキャッチアップしてきたか」
→ 勉強法、質問の仕方、改善サイクルなどを語ると、“育てやすい人材”に見える
よくある落とし穴:「成果がない=価値がない」と思い込む
実績とは、“大きさ”より“伝え方と文脈”
20代前半で、誰もが大きな成果を出せているわけではありません。
でも大丈夫。
✅ 評価されるのは
- 課題に対してどう向き合ったか
- チームの中でどんな役割を担ったか
- 同じミスをどう改善していったか
→ あなたが当たり前にやってきたことの中に、“評価される種”はきっとある。
まとめ:実績が求められるのは、構造の問題。でも、突破口はある
- 若手でも“実績”を求められるのは、企業側の“育てる余裕のなさ”が背景にある
- ポテンシャル採用は“嘘”ではないが、競争の中では“わかりやすい実績”が優先されがち
- 実績がなくても、“伝え方と文脈”次第で評価される
- 大切なのは、「ない」と決めつけず、“あるものを伝わる形に変換する”力
あなたの価値は、過去の数字だけじゃない。 これまでの経験を、言語化しよう。 それが、“実績ゼロ”というラベルを剥がす第一歩です。



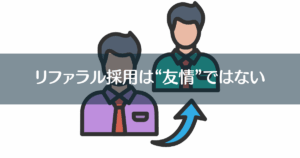
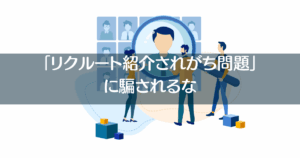



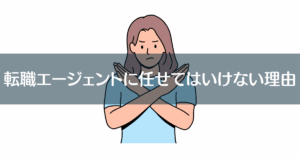
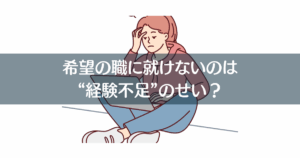
コメント