── 任されているつもりが、ただ“放置”されているだけかもしれない
「裁量あるって聞いたのに、なんか違う」って思ってない?
- 入社時に「裁量があります」と言われた
- 若手でも挑戦できる環境、って聞いていた
- でも、実際は放置されているだけな気がする
「なんでもやっていいよ」は、自由?責任?それとも丸投げ?
「失敗しても大丈夫」と言われたのに、何もフォローがない
「育てる気あるのかな?」と感じる日々
そんな“違和感”を感じているあなたへ。
この記事では、「裁量=自由=成長」という構図をいったん疑ってみるところから、
本当の意味での“成長できる環境”を見極めるヒントを探っていきます。
なぜ「裁量=良いこと」と思い込んでしまうのか?
特にベンチャーやスタートアップでは、
「裁量があります」という言葉がポジティブワードとして使われがちです。
◆ 若手=裁量がある=成長できる、という刷り込み
- 大手にはできないスピード感
- 社長直下、事業責任、マーケ戦略を任せられる
- 自分の力を試せる!
──こうしたイメージに惹かれて入社する人も多いはず。
でも、実態としては
“裁量”の名のもとに、“放置”されているだけ
そんな環境があるのも事実です。
「裁量」と「放置」の違いとは?
これを見極めるには、“裁量の裏側”にある構造を見抜く必要があります。
◆ 良い裁量=「任せる+伴走する」
- 目標が明確に共有されている
- 試行錯誤にフィードバックがある
- ミスしても一緒にリカバリーする文化がある
→ これは「育てるための裁量」です。
◆ 悪い裁量=「丸投げ+責任は自己完結」
- 何をしていいかわからない
- 相談しても「自分で考えて」しか返ってこない
- ミスが起きたとき、個人のせいにされる
→ これは「育成の責任放棄=放置」です。
「任せてくれる」のと「放り出される」のは、まったく違います。
苦しいと感じたときにできる3つのアクション
「放置かも…」と感じたとき、以下のステップで現状を整理してみてください。
◆ ① ゴールと責任範囲を明確にする
- 自分は何をゴールとすべきか
- どこまでが自分の裁量で、どこからは相談すべきか
→ 上司と一度“共通認識”を作るだけでも、ストレスはかなり減ります。
◆ ② 相談したい時に「聞いていい雰囲気」があるか観察する
- 忙しそうでも、声をかけたら対応してくれるか
- 「まず自分で考えてから来てね」は、本当に考えてきたことを聞いてくれるか
→ “相談しにくい空気”が続くなら、長期的にはしんどくなっていきます。
◆ ③ 「学び」のトレースができているか確認する
- 昨日の自分と今日の自分で、何が変わった?
- それを、誰かと共有できる?言語化できる?
→ 「裁量がある」のに学びが積み上がっていないなら、それは環境の問題かもしれません。
よくある反論:「いや、裁量こそ若手の特権でしょ?」
たしかに、“任せてもらえる”という経験は、若手にとって大きなチャンスです。
でも、それは「任せられる準備」が整っている前提でこそ活きます。
- 任せ方が雑だったり
- 相談する文化がなかったり
- そもそも教育体制が崩壊していたり
そういう状態での「裁量」は、育成ではなく放棄です。
育成責任を果たす覚悟があって、はじめて“裁量”は機能します。
まとめ:「裁量」は、万能な成長装置じゃない
「若いうちは裁量がある方がいい」
──そんな空気の中で、自分を責め続けてないですか?
- 自分で考えろと言われたのに、成果が出ない
- チャンスだと思っていたけど、孤独で苦しい
- 本当に“裁量”なのか、分からなくなってきた
そんなときは、自分を責める前に、環境の構造を疑ってみてください。
「裁量がある」って言葉に、だまされなくていい。
あなたは、放置されるために働いてるんじゃない。
成長するために、働いているんです。

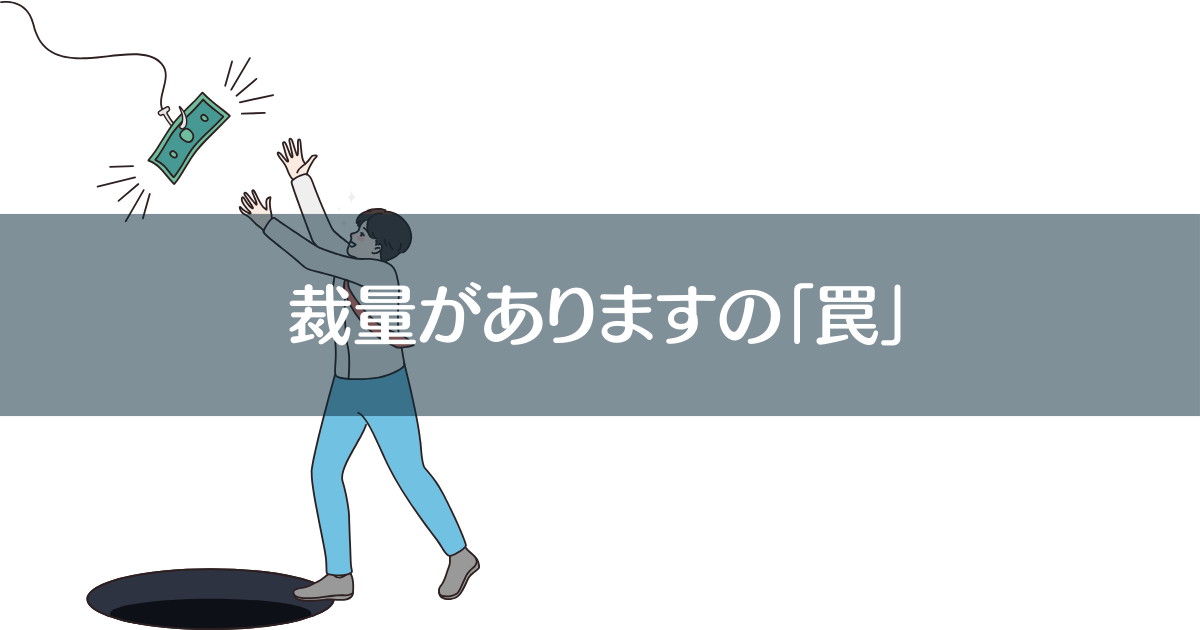

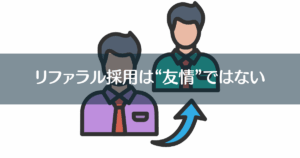
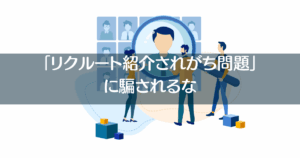

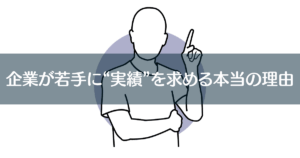


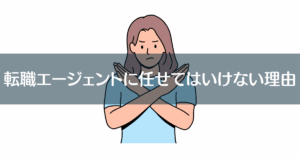
コメント